こんにちは、薬剤師ちょこ(@yakuzaishi.choko)です。
利尿薬の6つの分類の特徴って何だっけ?
と思っている方に向けて、利尿薬6分類の特徴について簡単に解説します。
- 利尿薬6分類の特徴
・分類①:炭酸脱水酵素阻害薬
・分類②:浸透圧利尿薬
・分類③:ループ系利尿薬
・分類④:サイアザイド系利尿薬
・分類⑤:カリウム保持性利尿薬
・分類⑥:バソプレシン受容体拮抗薬
今回の記事では、利尿薬6分類の特徴を1分ほどの動画で解説した内容を文字起こししたものです。
(※動画と内容が少し異なる場合もあります)
「文章で読みたい人」や「スキマ時間で確認したい人」はぜひ活用してください。
利尿薬6分類の特徴を動画で確認!
今回、文字起こしした動画はこちらの動画です。
↓この動画はInstagramに掲載したものです。
動画で一度確認したい!という人は上記をクリックしてご覧ください。
他の媒体から見たい方は、下記をクリックすると見ることができます。

それでは、解説していきます!
利尿薬6分類の特徴
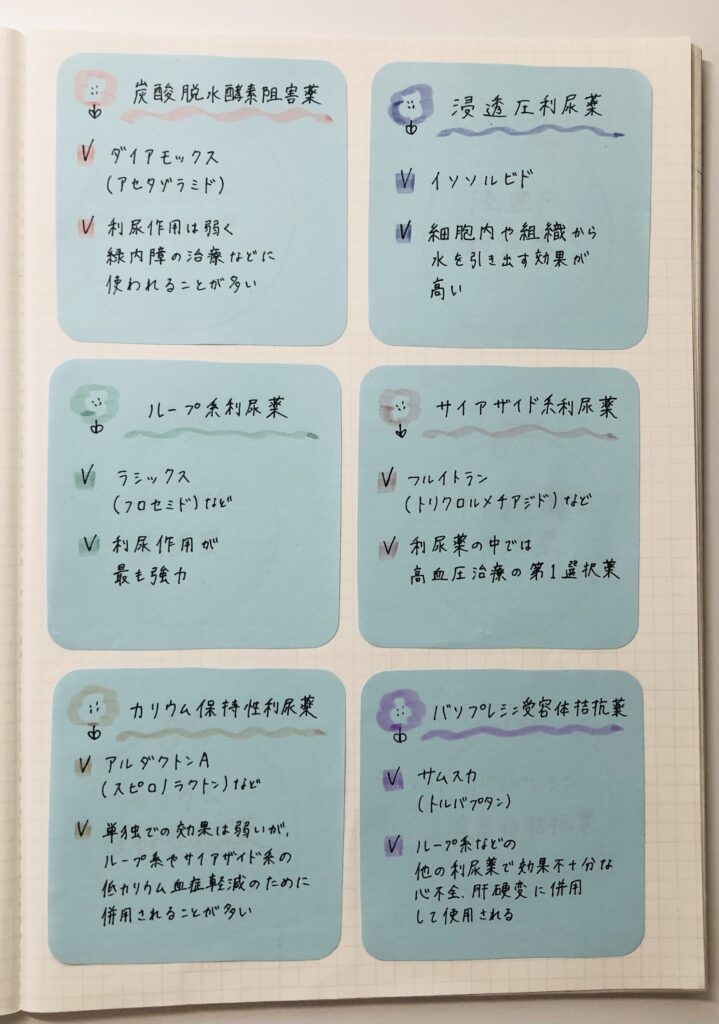
今回は、
利尿薬6分類の特徴
について解説します。
分類①:炭酸脱水酵素阻害薬

1つ目の違いは、炭酸脱水酵素阻害薬。
ダイアモックス(アセタゾラミド)
利尿作用は弱く緑内障の治療などに使われることが多い
です。
分類②:浸透圧利尿薬

2つ目の違いは、浸透圧利尿薬。
イソソルビド
細胞内や組織から水を引き出す効果が高い
という特徴があります。
分類③:ループ系利尿薬

3つ目の違いは、ループ系利尿薬。
ラシックス(フロセミド)、ダイアート(アゾセミド)、ルプラック(トラセミド)
利尿作用が最も強力
という特徴があります。
分類④:サイアザイド系利尿薬

4つ目の違いは、サイアザイド系利尿薬。
フルイトラン(トリクロルメチアジド)、べハイド(ベンチルヒドロクロロチアジド)、ヒドロクロロチアジド
類似薬:ナトリックス(インダパミド)、ノルモナール(トリパミド)、バイカロン(メフルシド)
利尿薬の中では、高血圧治療の第一選択薬
です。
分類⑤:カリウム保持性利尿薬
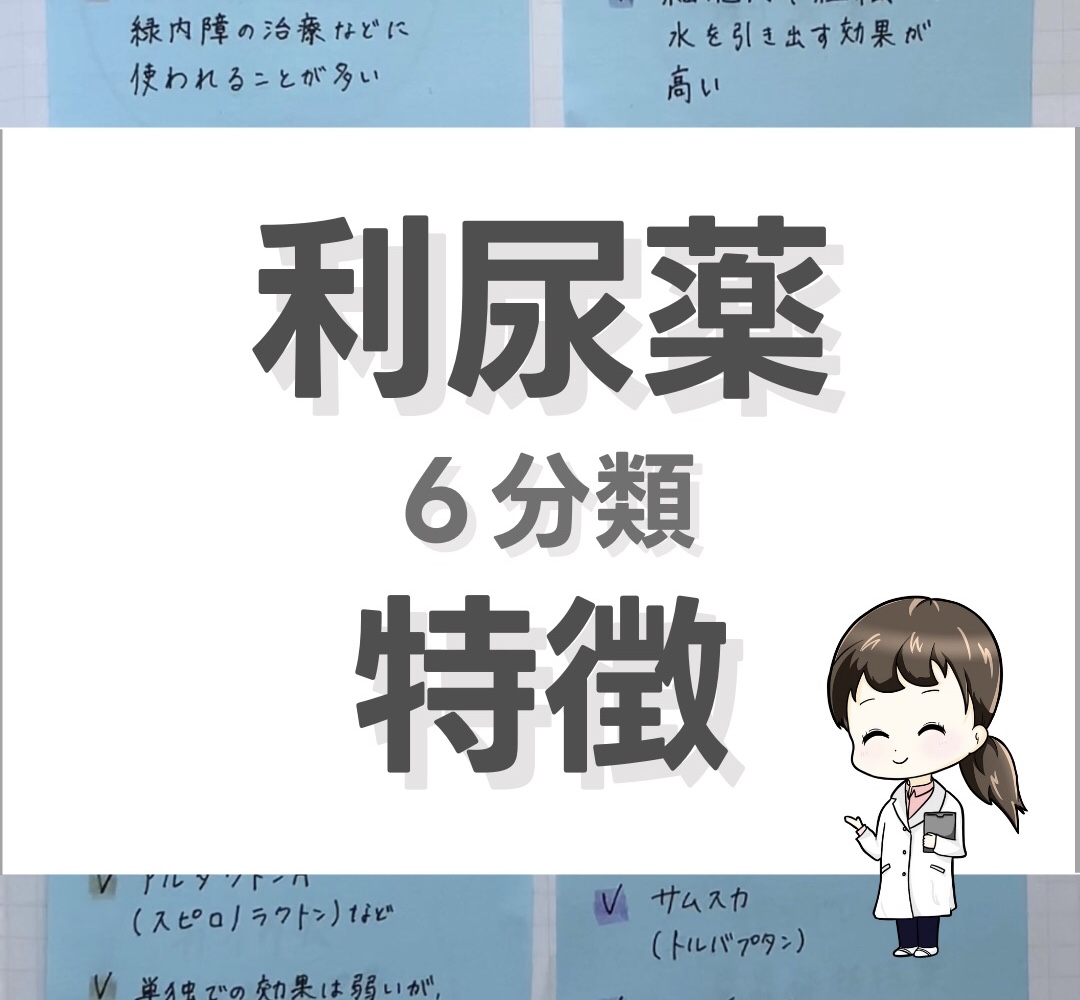
5つ目の違いは、カリウム保持性利尿薬。
アルダクトンA(スピロノラクトン)、セララ(エプレレノン)、ミネブロ(エサキセレノン)、トリテレン(トリアムテレン)
単独での効果は弱いのですが、ループ系やサイアザイド系使用時の低カリウム血症軽減のために、併用されることが多い
です。
分類⑥:バソプレシン受容体拮抗薬

6つ目の違いは、バソプレシン受容体拮抗薬。
サムスカ(トルバプタン)
ループ系などの他の利尿薬で効果不十分な心不全、肝硬変に併用して使用
されます。
もう少し詳しく知りたい人はInstagramの投稿をチェック!
もう少し詳しく知りたい!という人は、
Instagramで投稿しているこちらの記事をご覧ください。

Instagram(@yakuzaishi.choko)でも仕事が楽しくなる薬学知識を発信しています♪
見に来てもらえると嬉しいです
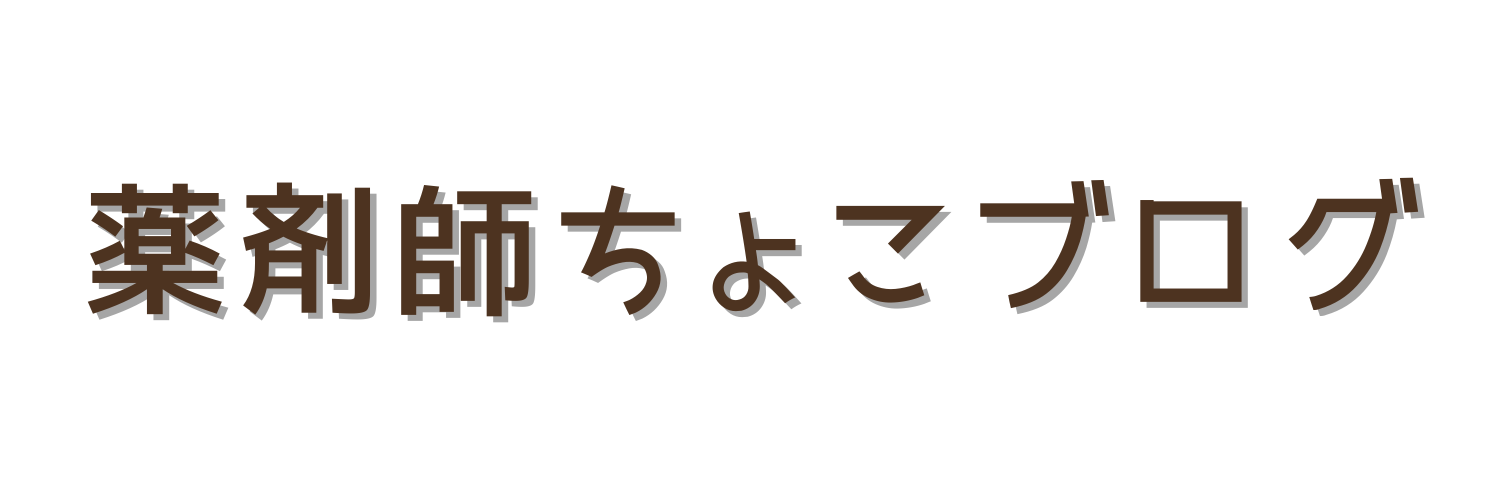
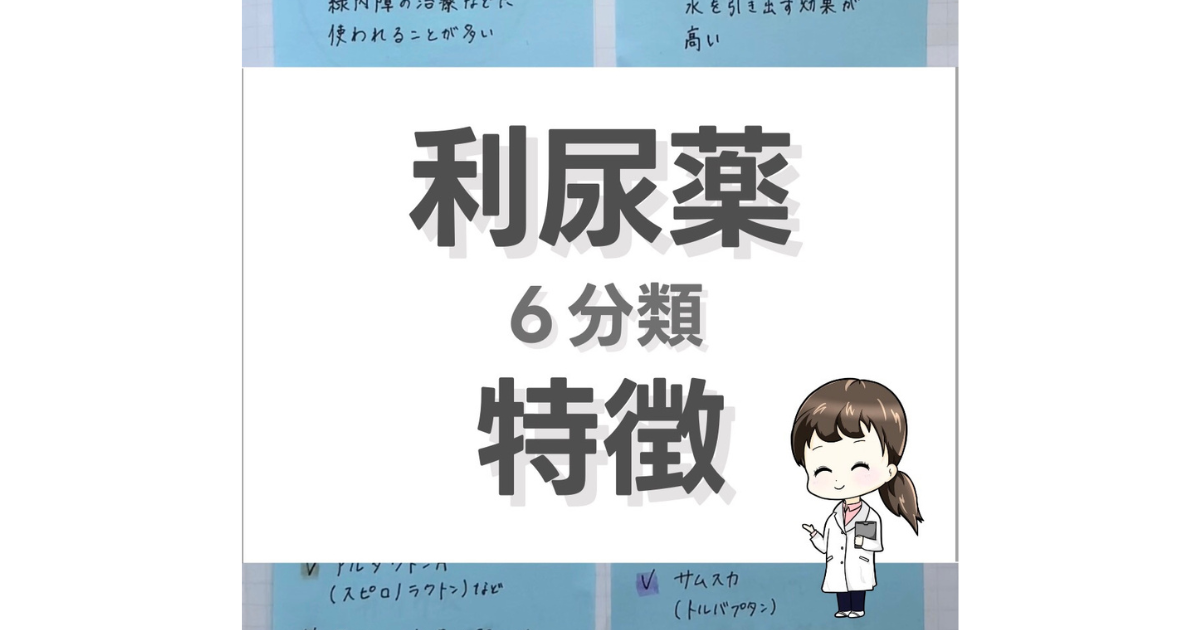
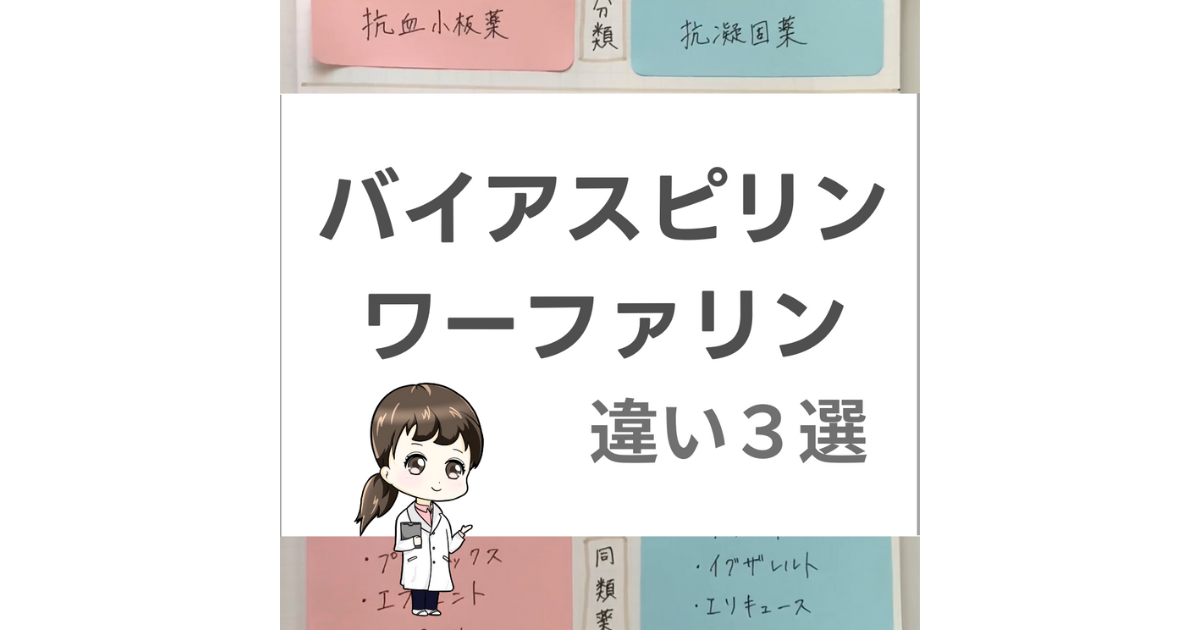
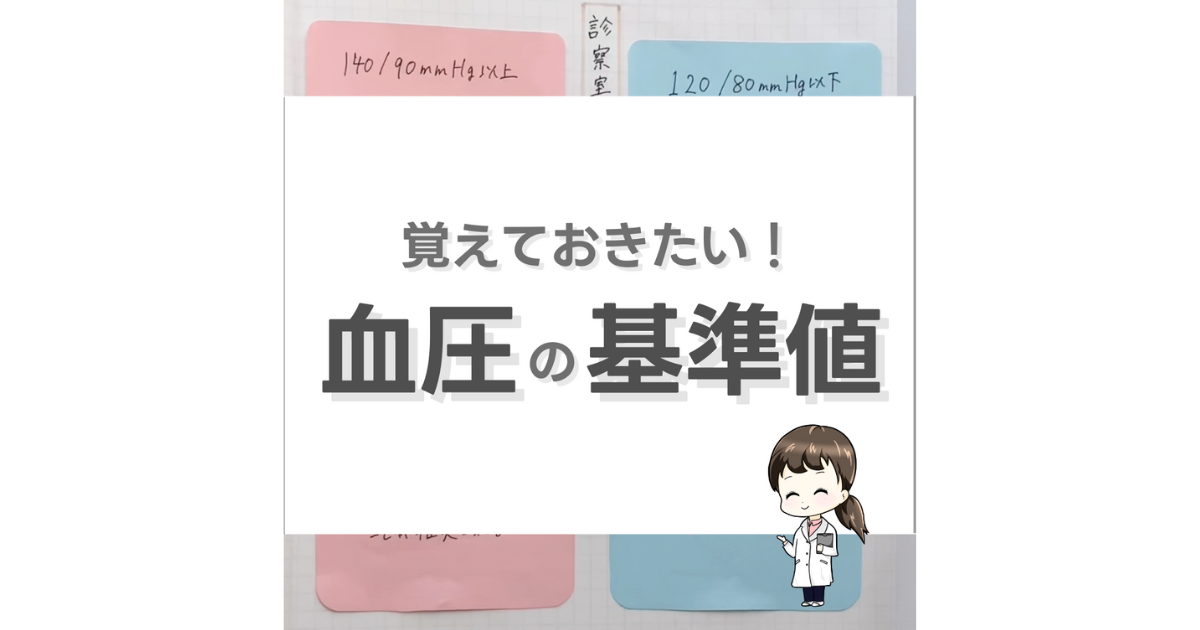
コメント